☆いま国立大学が危ない 小泉流「改革」に波紋
.しんぶん赤旗12・9-up12/10-
---------------------------------------------------------------
しんぶん赤旗12月9日号
いま国立大学が危ない
小泉流「改革」に波紋
”大変な爆弾落とされた”(国大協会長)
小泉流大学「改革」が、国立大学を戦後かつてない事態へ追い込んでいます。「六月には、大変な爆弾を落とされた」。十一月十五日の国立大学長懇談会で、国立大学協会(九十九大学)の長尾真会長(京都大学総長)はこうのべ、六月に発表された小泉内閣の「大学構造改革の方針」(「遠山プラン」注1)の波紋の大きさを強調しました。国立大学の独立行政法人化(独法化)を検討している文部科学省は九月、その「中間報告」をまとめ、来年三月までに最終報告をえてただちに法案準備に入るといいます。国立大学はどうなるのでしょうか。
すでに各地で統廃合
北海道では存続運動
「いつまでもあると思うな親と金」
工藤智則文部科学省高等教育局長は、学長懇談会でこうのべ、「(限られた)資源を最大限に活用した戦略的経営を進める競争的環境」づくりを強調しました。”一県一国立大学、各県に教育学部を設置”という原則を崩し、国立大学を大幅に減らす計画です。
すでに山梨大と山梨医科大、筑波大と図書館情報大が統合に合意しました。
五つある分校の統廃合を検討中の北海道教育大―。
「遠山プラン」が発表されると、札幌を中心とする道央圏への教員養成部門の集約案が急浮上し、分校の一つである釧路校は、廃校の危機に直面しています。
十一月、釧路校を擁する釧路市は、商工会議所、高校の校長会やPTAなどとともに、釧路校存続を求める団体署名運動を始めました。市民から「地域を知っている釧路校卒業の教師に教えてほしい」「付属の小中学校はどうなるのか」「釧路校がなくなると、教師を目指す生徒は札幌までいかねばならない」「学生がいなくなると地域経済は大打撃を受ける」など、切実な声が寄せられています。
島根医科大と島根大との統合問題を取り上げた、山陰中央新報九月二十四日付「論説」は、「国の財政負担を軽減するための経営効率化だけでは、大学を荒廃させるのではないか」と問題点を指摘します。
<注1>「遠山プラン」=(1)国立大学の再編・統合を大胆に進める→スクラップ・アンド・ビルドで活性化 (2)国立大学に民間的発想の経営手法を導入→新しい「国立大学法人」に早期移行 (3)大学に競争原理を導入→国公私「トップ30」を世界最高水準に育成。
国が評価し、競争させる
30大学に予算重点化
文科省は、国立大学を減らす一方で、国の評価にもとづく競争原理を導入して国公私立大学トップ三十大学を世界最高水準に育成すると打ち出しました。
「遠山プラン」などによれば、文科省に評価機関をつくり、各大学を審査・選定するとしています。その評価に応じて、研究資金を分野別上位三十の学部・学科だけに重点配分します。逆に、国の評価に値しない研究は、資金が不足し、変更・中止に追いこまれかねません。
岸田文雄文科副大臣は「論文の引用度数あるいはインパクトの度合い、競争的資金の獲得状況あるいは学会賞等々の受賞状況等」と評価の基準をのべました。(国会答弁、十月三十一日)。
日本共産党の石井郁子衆院議員は、「国が評価して学術研究を統制することは絶対やってはいけない」と批判。同時に、低温超伝導の研究やノーベル賞を受賞した白川英樹教授の研究を例に、「その時代でだれも振り向かないような研究」「非常に地道な研究」「偶然のつみ重ねの研究」を学問的に保障する意義を訴えました(同日)。
すでに、文科省は「世界最高水準の大学づくりプログラム」として、重点資金二百十一億円を来年度予算概算要求に入れました。
三輪定宣千葉大学教授は、いいます。
「『遠山プラン』は国会や大学人の議論を無視して突然出てきたもので、手続き的にも問題です。内容も、地方大学の役割を軽視し、国が競争的な環境で大学と研究を選別するなど学問の自由をおかすものです。日本経済が国際競争に勝てる研究かどうか、そうでなければ予算に差をつけてスクラップする。そんな競争原理では、人文や社会科学研究、長い時間が必要な基礎研究が軽視され、学術研究は衰退するのではないでしょうか」
民間的経営手法を導入
「上位下達」を強める
文科省の「中間報告」はっどうでしょうか。
「独立行政法人化で、上位下達が強まり、うちの研究所はまるで会社みたいになってしまった」
こんな声が、今年度から独法化された、国の試験研究機関で働く研究者から早くもあがっています。
「報告」の描く「国立大学法人」像は、大学運営に民間的発想を導入し、大学に企業経営の原理を持ち込もうとするものです。
「報告」では、学長の強いリーダーシップでトップダウンの意思決定の仕組みをつくり、学長の選考過程や大学役員に学外者を多数参画させ、民間的な戦略的大学運営を実現するとしています。
これまで国立大学の大学運営は、学長を全教員で選出し、人事や予算、カリキュラムなど大学にかかわる問題は、教員で構成する評議会や教授会で議論し、決めてきました。これは、憲法で保障された「学問の自由」と戦前からのたたかいで確立された「大学の自治」にもとづく大学独自の自主的で民主的な運営です。
国立大農学系学部長会議(四十九大学で構成)は十月十七日、「中間報告」にたいする意見書を発表。そこでは、学外者の役員会等への参加について「一律の方式を押し付けるのではなく、各大学の自主的な選択と決定権を認めるべきである」、部局長などの教員選考についても「従来通り、『部局教授会の審議を経ること』を明示すべきである」と主張しています。
大学の目標も計画も
文科相が決める
さらに文科省の「中間報告」の大きな問題点は、「大学運営の自主性・自律性や教育研究の専門性を尊重」とのべながら、逆に、国の関与を強める独立行政法人通則法(注2)の枠組みを基本的に受け入れたものになっている点です。
「報告」では、各大学は国家政策を「踏まえて」目標案をまとめますが、それを策定するのは、文科相です。各大学は、その目標にもとづいて計画を立てますが、認可するのは文科相です。計画の達成度や大学の運営全体を評価するのは文科省の大学評価委員会(仮称)で、評価の結果は、競争的環境の醸成」の観点から各大学の予算に反映させる仕組みです。
国立大学理学部長会議(三十二大学で構成)は十月二十六日、「中間報告」について見解を発表しました。
見解は「(文科省が中期目標を定めることについて)大学における教育研究の方向付けが、その時々の政府の方針に左右されるおそれ」があり、「息の長い研究の推進が必要な理学のような基礎科学にとっては、研究政策の変更により長期的進歩が阻害されるおそれがある」「(中期目標の策定は)教育研究の自由な発想や、大学人自身による企画立案を尊重して『各大学自身が作成する』とすべき」だとしています。
「こんな制度では、大学の予算や人事も、特定の分野に重点をおいたゆがんだものになるでしょう。経営に教学を従属させ、国の管理の下に、大学をがんじがらめにするものです。これでは、大学全体の活力も弱まっていく。トップ三十大学を頭に、大学の序列化もすすむ。受験戦争も激化する。日本の高等教育にかける予算の対GDP比は、OECD加盟国平均が1・3%のところ、0・4%という低さです(図)。改革というなら、大学予算の抜本的な増額をするべきです」(前出・三輪教授))
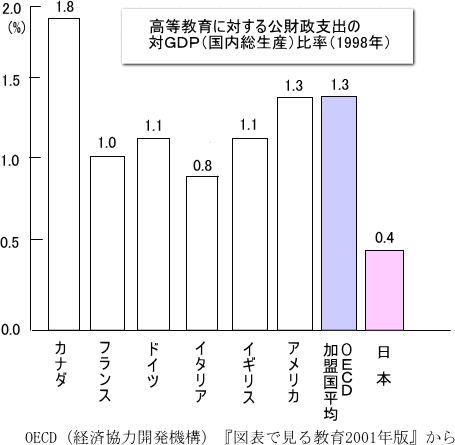
<注2>独立行政法人通則法=(1)主務大臣は、三年以上五年以下の期間で、独立行政法人が達成すべき目標を決め、独立行政法人は目標にもとづいて計画を作成し、主務大臣の認可を受ける (2)主務省に、独立行政法人の実績を評価するため、評価委員会を置く (3)国は、評価委員会の意見もとづき、予算の範囲で独立行政法人に資金を支給。法人は企業会計原則にもとづいてそれを執行することができるはど。
予算増に耳貸さず
強引に「改革」押しつけ
石井郁子衆院議員は、国会審議で、小泉内閣の国立大学の構造改革について「日本の学術研究の基盤を揺るがしかねない問題」といち早く指摘し、政府は高等教育にたいする予算の増額という喫緊の課題を放棄していると批判しました。
さきの学長懇談会で、地方大学の学長から「留学生のための予算の目減りが激しい。なんとかならないのか」という切実な意見がでたとき、それまで居丈高だった文科省の工藤局長は平謝りするしかありませんでした。
いま多くの大学人が、思い切って高等教育予算を増やし、国立大学の貧困な教育研究の環境を改めることを求めています。
国立大学の独法化は、各大学が学費を決めることになるため、大学間、学部間格差を生み、学費値上げにも道をひらくものです。
小林昌弘全学連委員長は「学費値上げは、学生に重大な影響を与えます。学生の生活と学問の自由を守る体場から、この問題を学び、積極的に行動していきたい」といいます。
懇談会で、ある地方大学の学長は「国立大学の独法化は、あいまいで問題点が多い。大学の自治と長い歴史をふまえて、もっと議論の時間が必要ではないのか」と訴えました。拙速で強引な「改革」押しつけでなく、全大学人の意見をふまえた民主的な大学改革こそ求められています。