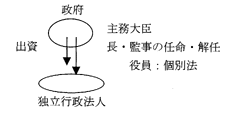
| フォーラム 東大改革<No.20 1999年8月19日> |
東大改革 東職特別委員会
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学職員組合
TEL/FAX 03-3813-1565 E-mailアドレス:bh5t-ssk@asahi-net.or.jp
独立行政法人とはなにか?
―通則法の仕組みについて―
―目次―
(1)設立 (2)業務運営 (3)評価制度と目標期間終了時の検討 (4)企業会計原則 (5)人事管理と定員管理(特定行政法人の場合)
|
1.はじめに
国立大学の独立行政法人化をめぐる動きが加速している。「独立行政法人通則法」(1999.7.16. 以下、通則法)が公布され、その内容が明らかになるなかで国大協などからは「特例法」による通則法とは別の形の学術法人の構想なども出始めている。通則法の規定する独立行政法人はあまりに大学の実情に適しないというのがその理由である。しかし、他方で、藤田論文に示されたような通則法を前提とする独立行政法人化の可能性もまだ消えたわけではない。
では、通則法で定める独立行政法人とはどのような仕組みの組織になるのであろうか。法律に則して、簡単にその内容を見てみることにしよう。
1)改革基本法における独立行政法人制度
「独立行政法人」という概念が最初に法律に登場したのは、中央省庁等改革基本法(1998.6.12. 以下、基本法)である。基本法において独立行政法人制度の基本的なスキームが定められ、それを具体化するものとして通則法は制定されたのである。したがって、当然のことながら、通則法の基本的な枠組みは基本法の規定するところ(とくに38条、39条)とまったく異ならない。
この立法の経緯から明らかなことは、通則法の独立行政法人制度は、もともと大学がその対象となることが予定されていなかった昨年の春に、行政改革会議における行政の「企画立案機能」と「実施機能」とを切り離して、後者を独立行政法人化(エージェンシー化)するという考え方に基づいているということである。基本法における独立行政法人は、主務官庁で決定される基本方針(企画立案)を忠実に、かつ効率的に実施する機関として構想されているのである。通則法が、後述するように、大学の実態とはおよそ相容れないトップ・ダウン型の組織として設計されているのはこうした理由による。
念のために基本法が定めている独立行政法人制度の基本的な項目を挙げておこう。
①運営の基本等に関する法律の制定(37条)
②運営の基本:「中期目標」、「中期計画」、「企業会計原則」、評価、効率化(38条)
③二段構えの「評価委員会」制度: 府省および総務省に置く。(39条)
④職員の身分:必要なものに公務員型、現業型労使関係法(40条)
2)通則法における独立行政法人
独立行政法人は、公共的な事業を「効率的かつ効果的に行わせるために」、「個別法」によって設立される(2条1項)。ここで「個別法」というのは、通常の言葉で言えば設置法である。
個別法で設立が決定されると主務大臣は、設立委員を任命して設立事務にあたらせ、同時に独立行政法人の長と監事を指名・任命する(14、15条)。独立行政法人の財政的基礎は政府の出資によって確保される(8条)。役員は個別法によって定められる(18条)が、主務大臣は長および役員を解任する権限も有している(23条)。
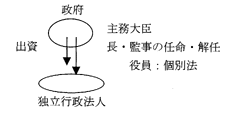
「実施機能」を担当させる組織に相応しく、担当省庁のイニシアティブで独立行政法人はつくられるのである。学長や部局長を大学管理機関が選考するという教特法に基づいている現在の大学の慣行とはまったく異なる方式が取られているわけであるが、こうした仕組みは行政庁の実施機関についての定めだと理解すれば当然とも言える。また、長の選任の基準(20条1項)も大学には相応しくないという見方もある。
通則法第3章の「業務運営」に関する規定は非常に重要である。基本法にもすでに示されていた枠組みであるが、これは独立行政法人が独立行政法人であるための不可欠な規定と言うべく、「個別法」で安易に排除することは許されない部分である。まず簡単な図を示してから解説することにしよう。

独立行政法人の業務運営の制度的な要となるのは、主務大臣が決定する「中期目標」とこれを受けて独立行政法人が作成する「中期計画」である(29条、30条)。中期目標は、3年から5年のタームで決定され、「業務運営の効率化」など法の定める事項を含むものでなければならない。この目標-計画のシステムにおいて最も重要なポイントは、中期目標が「上から」、主務大臣によって決定されるという点である。独立行政法人が作成する中期計画は、当然、この目標に沿ってこれを具体化するものであり、しかも主務大臣の「認可」を受けなければならない(30条1項)。そのうえ主務大臣は計画期間中に「実施上不適当」となったときは計画の変更を命じることもできるのである(30条4項)。独立行政法人の「中期計画」はまったく独立性のないものであるという点に注意しなければならない。
念のために、「中期目標」と「中期計画」で定められるべきとされる事項を要約して掲げておこう。
「中期目標」で定められる事項
(29条2項)「中期計画」で定められる事項
(30条2項)①「業務運営の効率化に関する目標を達成するため」にとる措置
②「サービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため」にとる措置
③「予算(人件費の見積もりを含む)、収支計画及び資金計画」
④「短期借入金」
⑤ 財産の譲渡、担保
⑥「剰余金の使途」
⑦ その他省令で定める事項
ここで明らかなように、業務運営の効率化、財務内容の改善(効率化と同義と見てよい)が主務大臣が定める目標の重要なターゲットになっていることが分かる。“減量・効率化”が独立行政法人制度のキーワードである。そしてそれと同時に、「業務の質」の向上が求められる。少ない資源で良いサービスを、ということになれば当然、厳しい職場管理や教官へのノルマの増加がもたらされる。そして、最大のポイントは、目標を受けて独立行政法人の側で決める「計画」が、上から与えられた「目標を達成する」ことを目的として作成されるということである。
独立行政法人がその名に反して独立性の非常に弱い機関であるということが示されている。しかし、ここでも独立行政法人が「実施機能」を担う機関として制度設計されているということを想起すれば、<独立行政法人の非独立性>というねじれも了解することができるであろう。
こうした主務省の監督に加えて、主務省と総務省のもとに置かれる評価委員会が独立行政法人の業務を不断に評価し、独立行政法人と主務大臣に対して意見、勧告を述べるという評価システムが創設される。前者の評価委員会については通則法12条に、後者の評価委員会については通則法32条3項に「審議会」という名で規定されている。後者が総務省に置かれる評価委員会であるということは前述の基本法の規定から知られる。
独立行政法人の日常的な運営の評価でまず重要な点は、「年度計画」である(31条)。独立行政法人は中期計画を各年度にブレイクダウンした年度計画を作成し、これに基づいて業務を遂行するわけであるが、毎年度評価委員会がその業務実績を評価し、「審議会」にその結果を通知すると同時に、独立行政法人に対して通知し、必要な場合には改善勧告を行うことができる(32条3項)。そして「審議会」は評価委員会に対して評価のあり方、内容に関して意見を述べることができる(同5項)。評価委員会の評価や勧告はいずれも公表される(4項)。
中期目標の期間の終了時には、独立行政法人は、「事業報告書」を作成しなければならない(33条)。また、評価委員会は、目標期間の全体についての総合的な評価をすることとされ(34条)、主務大臣は、「当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずる」(35条1項)とされている。この最後の規定はとくに重要である。独立行政法人の存続、改廃が3年から5年ごとに検討されるということになるからである。こうした主務大臣の検討とは独立に、「審議会」が「事務及び事業の改廃」に関する勧告を行うこともできるとされている(35条3項)。省内利益によって不要な事業が独立行政法人として継続させられるのをチェックすることがその趣旨であろう。
ここで、中期目標終了時の検討が単なるルーティンとしてなされるのではないことは、法成立時の国会の付帯決議からも知られる。これによれば、主務大臣が行う検討のための基準を2003年度までにつくって、この基準に基づいて「独立行政法人の存廃、民営化」を決定することとされ、また独立行政法人の形態としては今後の見直しにおいて「できる限り特定独立行政法人[いわゆる公務員型]以外の法人とするよう努める」とされているからである。現在国立大学が独立行政法人化において想定されているのは「特定独立行政法人」の形態であるが、これは過渡的な形態と見なされているのである。
改めて、独立行政法人制度が、行政の減量化と効率化とを目的としているという点を思い起こさないわけにはいかない。
独立行政法人制度が行政の減量化と効率化の手段として制度化されたものであるとすれば、独立行政法人の財務管理が、国家財政の合理化、効率化の要請に応えるものでなければならないことは自明の理である。
独立行政法人は一部にある誤解のように独立採算性を取るものでは決してないし、また「企業会計原則」を取る(37条)からといって民間私企業のごとくに自由な財務運営がなされるわけでは決してない。財政的な基礎は前述のように政府出資によるし、また業務運営のための財源の「全部または一部」は政府の予算から支出される(46条)からである。「実施機能」を担当すべき独立行政法人は、あくまでこれまで政府の業務としてなされていた事業を引き続いて行うのであるから、政府と離れて民間企業のように自由に運営されるのでないことはまったく明らかなのである。
財務諸表に関する監事および会計監査人の監査(39条以下)、評価委員会の意見(38条2項)、主務大臣の承認(同1項)、官報への公示(同4項)など財務・会計が厳しく監視されることは当然として、自由度が高まると一部で期待されている剰余金の使途についても厳しい枠がはめられている。
「企業会計原則」を採用するために毎年度の「利益」、「損失」が計上され、繰り越すことが可能となるが、問題の「剰余金」は「中期計画」にその使途を定めておかなければならない(30条2項6号)。年度ごとに利益が出たからこれを剰余金として使うというようなことはできない仕組みになっているのである。計画期間中に利益、損失は政府の交付金との兼ね合いで調整される可能性が高いし、仮に剰余金を計上できるとしても主務大臣の認可が必要なのである(30条1項)。
その他、借入金、債権発行(45条)、財産処分(48条)などの規定もあるが、全体として、独立行政法人の財務・会計ルールは、必ずしも独立行政法人の財政自主権を高めるものにはなっていない。「企業会計原則」は、独立行政法人の自主的な運営を可能にするための手段であるというよりは、「実施機能」を担当する機関の財務の効率性を高める手段として導入されている、と見た方がこうした仕組みを素直に理解することができる。
大学が独立行政法人化したら、財政的な自由度、柔軟性が高まると期待する向きがあるが、通則法の仕組みはそうした自主的な組織を想定しているわけではないのである。
大学が独立行政法人化した場合、職員の地位はどうなるのだろうか。「公務員型」(特定独立行政法人)になる場合には現状とそう変わらないのではないかと考えている人も多いようである。また、独立行政法人化した場合には「定員削減」から外れるので現状の定員を維持することができると思っている人もまだ多いようである。しかし、本当にそうなのであろうか。
「特定独立行政法人の職員及び役員は、国家公務員とする」(51条)。職員は「一般職の公務員」で基本的な地位は現在と変わらない。ただし、給与、勤務時間等は現行のように給与法、勤務時間に関する法律等によるのではなく、独立行政法人が独自の基準に基づいて決定することになる(57,58,59条)。法人が給与等の決定主体になるから、この点では民間の労使関係のような仕組みが必要になることになるが、国の機関であるので民間の労使関係法が適用されるのでなく、現在郵政や林野の現業部門に適用されている国営企業労働関係法(国労法)が名称を変えて適用されることになる(関係法律の改正のうち国営企業労働関係法の一部改正を参照)。つまり、給与、勤務条件は独立行政法人が決定する。その決定に関して職員団体(職員組合)が交渉し、労働協約を締結することができるというようになるのである。ただし、国労法の下では争議行為は禁止されている。
給与や勤務条件に関して、独立行政法人の裁量の幅が出てくるので現在よりも弾力化することは確かであろう。しかし、国家公務員の水準が参照基準とされる(57条3項、58条2項)のでこの裁量の幅はそれほど大きなものにはならない。
問題は、このそれほど大きくはない裁量の範囲で、どのように弾力化していくか、という点にある。給与については、「職務の内容と責任」に応じたものであり、「職員が発揮した能率が考慮される」とされている(57条1項)。こうした文言は国家公務員法の規定とそれほど変わるわけではないが、現在より能力主義的な色彩の強い制度が採用される可能性が高い。というのは、独立行政法人がその業務運営全体において財務の効率化を推進することが求められているからである。「中期目標」には「財務内容の改善」が規定され(29条2項4号)、「中期計画」の予算には人件費の見積もりを含むとされている(30条2項3号)。「人件費」は可能な限り切りつめることが求められているのである。他方で、給与の決定には、「当該独立行政法人の業務の実績」が参照基準の一つとされている(57条3項)。つまり「業務実績」(これをどのように測るのかなお明確ではない)が向上すればそれを給与に反映しようというわけである。<逆は逆>で、業務実績が芳しくないと認定されれば、給与は国家公務員より低めにしなければならないということになろう。
この両方の側面を総合すれば、こういうことになる。なるべく少ない人件費で高い効率を上げれば、いくぶんか給与の改善が生まれる。こうした仕組みは、職員に高能率を課す仕組みであると言える。また、総人件費を抑制しつつ、職員の能率を上げようとすれば、個人別の能力評価による賃金管理が導入されるということにもなるであろう。
では、定員の面はどうであろうか。給与に関して見たところからも明らかなように、不断に業務効率を上げるためには、厳しい定員管理がなされることが必至である。独立行政法人にも定員削減は及ぶ、というのは政府部内での了解であり、国家公務員としての定員削減計画から仮に外れるとしても、独立行政法人独自の定員削減が推進されることは火を見るより明らかである。独立行政法人制度そのものが「行財政改革」の手段なのであるから、独立行政法人になれば定員削減を外れるというのは幻想以外のなにものでもない。具体的には、「中期目標」、「中期計画」で定員管理も問題にされ、これは評価委員会、「審議会」の評価の対象となる。さらに、独立行政法人は毎年、職員の数を主務大臣に報告するものとされ、主務大臣はこれを毎年国会に報告しなければならない(60条)のである。
さらに言えば、独立行政法人は、前述のように、つねに非公務員型への移行、または民営化の可能性を視野に入れた検討の対象となりうるのであり、大規模な組織の「改廃」も空論ではない。そこで起こることは「定員削減」よりもずっとドラスティックな事態である。さらに、そこまで至らない場合でも、「人件費」の効率化という目標によって、正規の職員以外の派遣労働者やパートタイマーを活用するという方策が今以上に拡がることになるであろう。ちなみに、国会に報告されるのは「常勤職員の数」(60条)なのである。
3)要約
以上を要約すれば、通則法の独立行政法人とは、次のようなものである。
むすび -通則法と大学-
名古屋大学の池内了氏が、国立大学の独立行政法人化問題に関連して、アメリカの興味深い事例を紹介している。やや長文になるがその一部を引用しておこう。
「州立のワイオミング大学当局は、多数の外部評価委員からの意見を聴取して、今後5年間のアカデミック・プランを作成したのだが、そのドラフトに、物理学・天文学部を閉鎖することと、付属施設である天文台を売却するかリースに出すことを提案しているのだ。その理由は、“物理学・天文学部門は経済的に維持困難”というものである。その結果物理学専攻の学生は採らず、物理学は工学部や地質学部など他の学科の基礎科目として教えるだけになるらしい。(天文学だけならいざ知らず、物理学のようなコア科目をそう簡単に切り捨てていいのだろうか、と思ってしまう。)」(『科学』1999年6月号)
池内氏は、独立行政法人化の発想が“コスト-ベネフィット”方式にあり、そうした観点から大学が評価されるならこうした事態も生まれかねない、と警告を発しているのである。上述したように、通則法の独立行政法人は、まさに“コスト-ベネフィット”方式の効率化原理に立脚しており、「企業会計原則」による「利益」、「損失」の算定はまさにコストとベネフィットを明確にするための方式として発想されている。
大学は、本来、営利を目的とする企業体ではない。学問や科学の価値は、本来的に経済的な価値によって測ることはできないし、また経済的な価値に対して劣位にあるものでもない。大学に、「財政的な効率」を主要な目標として押しつけるなら、池内氏が紹介する事例のような学問の破壊と歪曲が生じるのである。
大学はまた、自立した研究者の自由なコミュニティでなければならない。研究者の自由と研究者間の平等がなければ、大学も学界も真の科学研究の場として成り立たない。大学における教育と研究は、そのような研究者の自由なコミュニティを基礎としてはじめて本来的なものとして成立するのである。
独立行政法人制度は、そうした研究者の自立性とは無縁な制度である。自由で自律的な組織とは正反対の、「上で」決定される「企画立案」に基づいて、決められた業務をもっぱら「効率的に実施する」のが、通則法に定める独立行政法人にほかならない。大学と独立行政法人制度とは、まるで相容れない“水と油”の如きものである。
最後にもう一度確認しておこう。通則法の「独立行政法人」なるものは、本来、一般の省庁の業務のうち、「実施機能」を担当させる組織として構想され、そのように制度設計されているのであって、大学に適用することはまったく想定されていなかったものである。独立行政法人制度と大学の実態とがあまりに合わないのは、そうした事情によっている。
簡明な結論は、別の目的でつくられたものを安易に大学に転用してはならない、ということである。
*なお、「通則法」では、具体的にある独立行政法人が設立される場合には「個別法」という設置法が制定されることになるということははじめに述べたとおりです。この「個別法」で大学に相応しい内容を決めればよい、という議論がありますが、これについては『改革フォーラム』の18号、19号の批判を参照して下さい。これを発行した後に、「通則法を適用した上で個別法等において質的に異なる特則を置く形式をとることは、法形式の明白な濫用である。」(山本隆司「独立行政法人」、『ジュリスト』1161号、133頁)という議論に接しました。
|
このフォーラムは、通則法の解説を意図しましたが、ぜひ、通則法そのものを読んでいただきたいと思います。
通則法は、「官報」135号、H.11.7.16.、『ジュリスト』1161号169頁に全文掲載されています。お問い合わせは、東職まで。 |
|
―ご意見・投稿は―
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学職員組合TEL/FAX03-3813-1565 E-MAIL:bh5t-ssk@asahi-net.or.jp |